
「オウンドメディアって、うちみたいな会社には関係ないでしょ?」
中小企業の人事担当者・広報担当者から、そんな声を聞くことは少なくありません。
確かに、動画コンテンツや特設サイト、SNS運用などを駆使した「採用向けオウンドメディア」といえば、大企業や急成長中のベンチャーが積極的に取り組んでいる印象があるかもしれません。
しかし実は、採用に苦戦している中小企業こそ、“オウンドメディア運用”のメリットと伸びしろが非常に大きいのです。
なぜなら、知名度がない会社は“待っているだけ”では応募されません。
求人広告を出しても埋もれ、せっかく採用サイトを作っても見られない。そんな経験はありませんか?
求職者は常に複数の企業を比較しながら、「どこに応募するか」を選んでいます。
そのとき、何を基準に選んでいるか?――それがまさに、“情報のある・なし”なのです。
つまり、オウンドメディアは「知られていない企業が、選ばれる企業になるための手段」であり、決して「余裕のある企業のブランディング遊び」ではありません。
この記事では、中小企業が採用活動においてオウンドメディアを活用すべき5つの理由と、現実的な始め方について、わかりやすく解説していきます。
「何から始めたらいいかわからない」「本当に効果あるの?」という方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
1. 採用向けオウンドメディアとは?
そもそも「オウンドメディア」とは、自社が“所有”する情報発信の場のことを指します。
企業のホームページやブログ、メールマガジン、SNSアカウント、YouTubeチャンネルなど、自社で運用・更新できるメディアはすべてオウンドメディアに含まれます。
その中でも、採用向けオウンドメディアとは、求職者(将来の応募者)に向けて、“会社の中身”や“働く魅力”を発信するコンテンツの集合体のことです。
「採用特設サイト」をはじめ、「社員インタビュー記事」「社内イベントの紹介ブログ」「職種紹介のInstagram投稿」などもすべて、立派な採用オウンドメディアの一部になります。
● 「採用サイト」と何が違うの?
よくある疑問に、「うちには採用ページがあるけど、それじゃダメなの?」というものがあります。
もちろん、採用サイトがあること自体は素晴らしいことです。
ですが、一般的な採用ページは「募集要項」「会社紹介」「エントリーフォーム」が中心で、情報が静的・一方向的になりがちです。
一方で、オウンドメディアの特徴は“更新し続けること”と“企業の中の人の声が伝わること”にあります。
- どんな社員が働いているのか?
- どんな仕事をしているのか?
- どんな価値観・文化を持っている会社なのか?
これらを“会社自身の言葉で、継続的に”伝えていくことで、応募の「前」に企業理解を深めてもらい、「この会社で働いてみたい」と思ってもらうのが、採用オウンドメディアの大きな目的です。
● 特別な仕組みは不要。小さな一歩からでも立派なメディア
「オウンドメディア」と聞くと、特別な構築や運用が必要に思えるかもしれませんが、そんなことはありません。
WordPressのブログ機能や、既存サイトの「お知らせ欄」、あるいは会社のInstagramアカウントでもOK。
重要なのは、「自社の魅力を、自分たちの言葉で伝える場があること」なのです。
では、なぜ中小企業こそオウンドメディアを活用すべきなのか?
次章では、その5つのメリットについて、具体的に解説します。
中小企業が採用オウンドメディアを持つ5つのメリット
「オウンドメディアの運用」と聞くと、「手間がかかりそう」「成果が見えづらい」と感じるかもしれません。
ですが、実は知名度の低い中小企業にこそ、大きなリターンをもたらすのが“採用向けオウンドメディア”です。
ここでは、中小企業がオウンドメディアを運用することによって得られる5つのメリットを紹介します。
① 知名度の低さを“信頼感”で補える
中小企業の最大のハンデは「知られていない」こと。
求人サイトや合同説明会でも、「初めて聞いた会社名」というだけで、スルーされてしまうのが現実です。
だからこそ、継続的な情報発信により「顔が見える会社」になることが重要です。
ブログ記事やSNSで日々の様子や社員の声を発信していれば、求職者のGoogle検索にひっかかり、自然と関心を持ってもらえるようになります。
② 「なんとなく不安」を払拭できる
中小企業への応募を迷っている求職者が感じているのは、条件の問題ではなく“情報が少ないことへの不安”です。
– どんな人が働いているのか?
– 本当に雰囲気はいいのか?
– ブラックじゃないのか?
こうした不安に対して、リアルな現場の声や日常風景を発信することで、求職者に「安心材料」を届けることができます。
③ 自社に合う人を自然に引き寄せられる
オウンドメディアでは、会社の価値観や文化を素直に発信することができます。
その発信に共感した人が応募してくるため、最初から「自社に合いそうな人」が集まりやすいのが特徴です。
結果として、採用のミスマッチが減り、入社後の定着率向上や人間関係のトラブル防止にもつながります。
「選ばれる」よりも「見つけてもらう」採用へ。それを実現するのがオウンドメディアです。
④ 採用媒体に頼りすぎず、コストを抑えられる
求人広告を出しても「掲載期間が終わればリセット」。
一方で、オウンドメディアは“積み上がる資産”です。
過去の記事や投稿がWeb検索に残り続け、求人広告では出会えなかった層との接点をつくってくれます。
少ない予算でも始められる点は、中小企業にとって大きなメリットです。
⑤ 採用だけじゃない!社員教育・営業にも波及効果
オウンドメディアは採用だけでなく、社内外へのブランディングツールとしても効果を発揮します。
- 新人研修で「会社理解」の教材として活用
- 社員が“自社の言葉”を持つことでエンゲージメントが向上
- 営業資料では伝えきれない「会社のストーリー」を外部に届ける手段として活用
情報発信が企業文化になれば、“採用”という枠を超えて、組織全体が強くなるのです。
実際に「何を」「どう発信する」のが効果的?
「オウンドメディアが大事なのはわかったけど、何を発信すればいいの?」
そんな疑問を抱えている人事・広報担当の方も多いかもしれません。
採用向けオウンドメディアで重要なのは、“求職者が知りたいこと”を、会社の言葉でリアルに伝えるということ。
演出や脚色ではなく、実態を丁寧に見せることで、「この会社なら信頼できそう」と思ってもらえるようになります。
● 採用オウンドメディアで発信すべき定番コンテンツ
- 社員インタビュー(どんな経緯で入社したか・仕事のやりがい・1日の流れ)
- 現場レポート(工場、営業先、事務所など、実際の仕事の様子)
- 新人研修や育成制度の紹介
- 社内イベント・日常の雰囲気(BBQ、歓送迎会、ランチの様子など)
- 社長やリーダー層のメッセージ(会社の想い、今後の展望など)
これらのコンテンツを通じて、「どんな人たちが、どんな想いで、どんな環境で働いているのか」が伝わると、応募前の不安を大きく取り除くことができます。
● 発信のコツは「きれいに見せる」より「等身大を届ける」
大企業のような高品質な動画や特設ページを用意する必要はありません。
むしろ、スマホで撮った写真に短いコメントを添えた投稿の方が、リアルで親近感が湧くこともあります。
たとえば──
- 営業部の朝礼の様子をInstagramにアップ
- 新人社員の研修風景をブログで紹介
- 「今日は社内でカレーの日でした」などの日常ネタもOK
求職者が知りたいのは、「この会社で自分が働いたときのイメージが持てるかどうか」です。
そのためには、“かっこよく作る”より、“ありのままを発信する”姿勢が大切です。
● 発信の頻度より、継続性と誠実さを
週1更新が難しければ、月1でも構いません。
大切なのは、更新が止まらず「生きている会社」として見えること。
1年放置された採用ブログは、それだけで「この会社、止まってる?」と不安を与えてしまいます。
少ない回数でも、継続することで“信頼の積み上げ”ができるのが、オウンドメディアの力です。
どんな媒体で始めるべき?ブログ?SNS?動画?
「オウンドメディア」とひとくちに言っても、使える媒体はさまざま。
どれを使えばいいのか迷う方も多いと思います。
答えは一つではありませんが、重要なのは“自社のリソースに合った形”で、無理なく続けられるものを選ぶことです。
ここでは、代表的な4つの媒体と、その特徴を紹介します。
● ブログ(採用ブログ・社員日記など)
- メリット:継続的な発信でSEO効果が見込める/社内でも運用しやすい
- 活用例:社員インタビュー、社内イベントレポート、1日の業務紹介など
- おすすめ:「すでにホームページがある」「文章に強いスタッフがいる」企業
WordPressなどCMSに投稿欄があれば、コストをかけずにすぐ始められます。
ストック型のコンテンツになるため、「積み上げていく資産」として有効です。
● SNS(Instagram/X(旧Twitter)/Facebook など)
- メリット:手軽に始められ、若年層との接点を持ちやすい/投稿に拡散性がある
- 活用例:職場の雰囲気、イベントの様子、日常の小ネタ、社員紹介など
- おすすめ:「写真を撮るのが好き」「こまめに発信できる人がいる」企業
とくにInstagramはビジュアルで伝えられるため、職場の“空気感”や“人柄”を伝えるのに最適です。
● 動画(YouTube/ショート動画など)
- メリット:臨場感とリアリティが伝わりやすい/スマホ1台でも始められる
- 活用例:社員の1日密着、現場紹介、社長メッセージ、職種別の仕事紹介
- おすすめ:「見学に来られない求職者に現場を見せたい」企業
動画は“伝わる情報量”が多いため、中小企業の「知られていない魅力」を補う強力な武器になります。
● 採用特化型ランディングページ
- メリット:エントリー導線を設計しやすい/SNSや広告との連携もしやすい
- 活用例:採用メッセージ、先輩の声、会社紹介+エントリーフォーム
- おすすめ:「採用に特化したページをしっかり作りたい」企業
広告流入やSNS経由の受け皿としても効果的で、“エントリーまでのストーリー設計”がしやすいのが魅力です。
● どれか1つからでもOK。「小さく始めて、続ける」ことが成功の鍵
理想を言えば、複数の媒体を連携させることが望ましいですが、まずは「始められるものから1つ」で構いません。
社内で更新しやすいフォーマット、自社のターゲットに合った発信場所を見極めて、無理なく運用することが何より大切です。
はじめの一歩は「小さく始めて続ける」こと
「オウンドメディア運用」と聞くと、つい気負ってしまいがちですが、最初から完璧な仕組みを作ろうとしなくても大丈夫です。
大切なのは、スモールスタートでいいから、まず“始めてみる”こと。
その上で、社内に少しずつ発信文化を根づかせていくことが、成果につながる近道です。
● 最初の一歩は「社員紹介」や「職場の風景」から
最も始めやすく、かつ求職者からの反応が得られやすいのが、社員紹介や日常の風景といった身近なテーマです。
- 「入社2年目の◯◯さんに聞きました」
- 「工場での1日の流れを追ってみた」
- 「月に1度のランチ会の様子をお届けします」
こうした投稿は、写真1枚+コメントだけでもOK。
内容よりも、“会社が外に向けて発信している”という姿勢そのものが、安心感を与えます。
● 発信は1人で抱えず「チームでゆるく」
担当者ひとりで更新を続けるのは大変です。
だからこそ、社内で“発信担当チーム”や“持ち回り当番制”などを導入し、無理なく続けられる体制を整えることがポイントです。
たとえば──
- 月1回、現場チームから1投稿ずつもらう
- 若手社員にInstagramの更新を任せる
- 営業日報の一部をブログに転用する
そうすることで、情報発信が社内のコミュニケーション活性化にもつながっていきます。
● 「質」より「継続」。コツコツ型が最も強い
初めは反応が少なくても気にしないでください。
オウンドメディアの力は、“発信の積み重ね”によってじわじわと効いてくるものです。
誰かがいつか、あなたの投稿を見て、エントリーしてくれるかもしれない。
その可能性をつなぐ橋が、オウンドメディアなのです。
まとめ:採用に強い企業は「発信している」
中途採用でも新卒採用でも、求職者が企業を知る手段は「求人票」だけではありません。
企業がどのような考えを持ち、どのような人たちが、どんな環境で働いているのか——そういった「空気感」や「ストーリー」にこそ、人は惹かれます。
だからこそ今、中小企業にとってもオウンドメディアの活用は“あたりまえ”の戦略となりつつあります。
社内の情報を外に出すことは勇気が要りますが、そこにこそ“等身大”の魅力があります。
完璧である必要はありません。共感できる発信、共鳴できる姿勢を伝えることで、企業と求職者の距離は縮まり、採用成功につながります。
今いる社員のためにも、これから出会う仲間のためにも。
あなたの会社らしい発信を、ぜひ今日から始めてみてください。
株式会社アトラボでは、中小企業に特化した採用支援を行っています。
採用サイトの設計・制作はもちろん、オウンドメディアやSNSの運用、コンテンツ企画まで一貫してサポート可能です。
「まずは何を始めればいい?」とお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
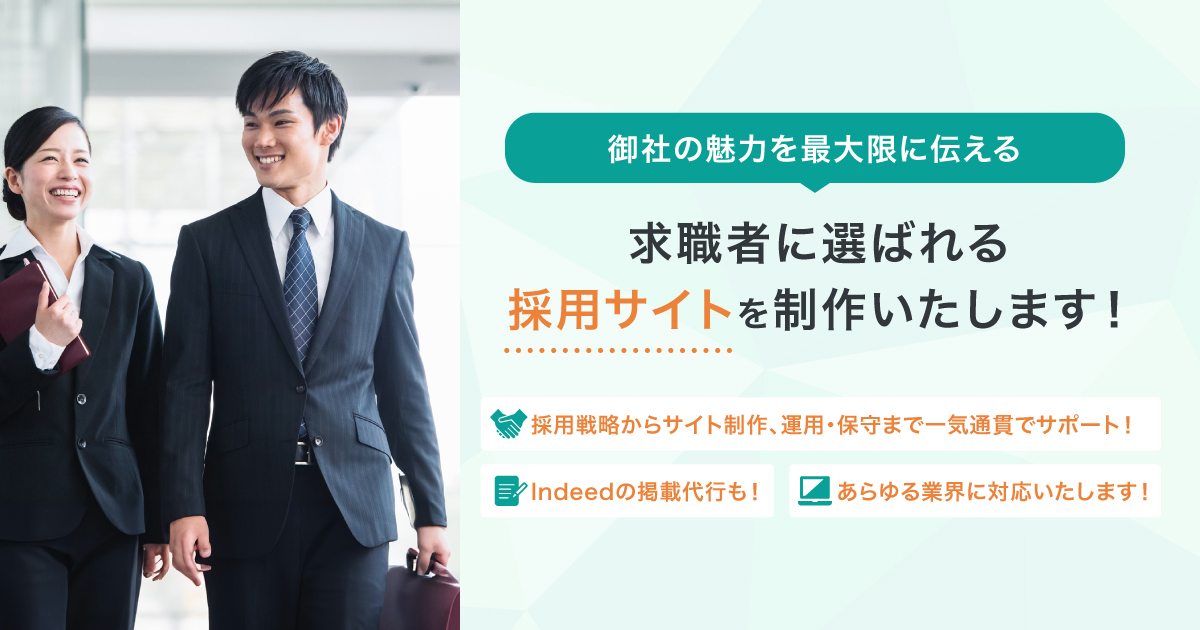




コメント