
新卒採用を行う中で、「業界はなんとなく知っているけれど、自社の仕事を理解してもらえない」と感じたことはありませんか?
実際、建設業・製造業・卸売業といった業種では、仕事の仕組みや役割が複雑で、学生にとってはイメージしづらいことが多くあります。
例えば建設業では、元請け・下請けといった構造や、現場・設計・管理など多様な職種が関わり合います。製造業では、完成品をつくるのではなく、部品加工や生産設備の製造といった“裏方”の仕事が多く、卸売業では「メーカーでも小売でもない中間業者」としての立ち位置が伝わりにくい。
このように、仕事内容や企業の役割が具体的に伝わらなければ、学生は応募前に「なんとなく違うかも」と判断してしまう可能性があります。
逆に言えば、仕事の仕組みをわかりやすく伝えられれば、興味をもってもらえる確率は格段に高まるということです。
本記事では、学生にとって「わかりにくい仕事」をどのように採用ページで見せていくべきか、その考え方と具体的な工夫を紹介します。
なぜ伝わらない?仕事の仕組みが複雑な3業種の共通点
建設業、製造業、卸売業に共通するのは、「最終成果物」と「自社の仕事」が直接的に結びつかないという点です。これは、学生や就職活動中の若者にとって、仕事を理解する上で大きなハードルになります。
建設業:元請・下請・職人の関係が複雑
建設業では、元請け・下請け・孫請けといったピラミッド構造が存在し、自社がどのポジションで、どの工程を担当しているかを説明しない限り、学生には「建設会社=家やビルを建てる会社」としか認識されません。
しかし実際は、工事の一部だけを担当する専門業者であったり、現場管理や安全管理が中心だったりと、仕事内容は大きく異なります。
製造業:部品・設備・BtoBだから見えづらい
製造業も同様に、「誰もが知る製品をつくっているわけではない」ケースが多くあります。
たとえば、家電に使われる小さなねじや部品、あるいはその部品を作るための機械や治具を製造している企業など、仕事の成果が一般消費者の目に触れないことが多いため、「何をしている会社なのか」が伝わりにくいのです。
卸売業:「メーカーでも小売でもない」役割の説明が必要
卸売業は、製造元(メーカー)と販売先(小売や事業者)をつなぐ中間業者としての役割を担っていますが、BtoBビジネスのため、学生がイメージしにくいのが現実です。
「商品を仕入れて売るだけ?」と思われがちですが、実際には在庫管理、物流手配、仕入先との交渉、販促支援など、業務は多岐にわたります。
これらの業種では、「当たり前すぎて説明していないこと」が、求職者との情報ギャップを生む要因になりがちです。
まずは自社の仕事を、どのように社会や製品とつながっているかという“位置づけ”から丁寧に示すことが大切です。
「仕組みを見える化」することで変わる志望度
求職者、とくに新卒学生は「何をする会社なのか」「どんな役割を担っているのか」が理解できないと、そもそも興味を持ちづらくなります。
逆に、業界全体の流れの中で自社が果たしているポジションや、入社後に自分が関わる仕事の流れを知ることで、「面白そう」「ここで働いてみたい」と思う気持ちは大きく高まります。
たとえば、製造業であれば「完成品ではなく“装置”を作っている」ことを説明し、さらに「その装置がどんなモノづくりを支えているのか」まで視点を広げて伝えると、学生の興味の幅も広がります。
建設業であれば、元請・下請といった構造だけでなく、「現場が完成するまでの全体工程の中で自社がどの役割を担っているのか」「どう現場を支えているのか」を見せることで、理解と共感が生まれます。
「なるほど、こういう仕組みなんだ」と納得してもらえるだけで、志望度が変わる──それが“見える化”の最大の効果です。
実際、「自分の仕事がどんな役割なのかを入社前に知っておけたのが安心材料になった」という新卒社員の声も多く、選考への意欲や入社後のミスマッチ防止にもつながります。
採用サイトで「仕組み」を伝える4つの方法
自社の仕事や業界の構造が複雑な場合でも、採用サイト上の工夫次第でわかりやすく伝えることが可能です。ここでは、新卒学生にも理解しやすくなる「仕組みの見える化」アプローチを4つご紹介します。
1. 業界全体の構造図を掲載する
自社単体の説明だけではなく、業界全体の流れや構造の中で自社がどのような役割を担っているのかを示す図解を掲載しましょう。たとえば「〇〇業界の流れ」「建設業界の受注構造」など、図を使って全体像をつかませるだけで理解度が一気に深まります。
2. 製品やサービスの「使用場面」を紹介する
とくに製造業・卸売業では、作っている製品が「最終的にどこで・誰に・どんなふうに使われているか」を見せると、イメージが膨らみます。
BtoB企業であっても、最終ユーザー視点での説明を加えることで、学生にも自分ごととして理解されやすくなります。
3. 仕事の流れを図解・チャートで見せる
「営業→設計→製造→納品→保守」など、自社内での業務フローをチャート化して見せる方法です。さらに部署ごとの役割や関係性を記載することで、「この会社ではこうやってモノが動くんだ」と学生がイメージしやすくなります。
4. 若手社員の関わるプロジェクト紹介
実際のプロジェクトや現場の流れを、若手社員の関わった事例として紹介するのも効果的です。時系列に沿って「どの部署がどう動き、最終的にどんな成果が出たか」を紹介すれば、業務内容も仕組みも同時に伝わります。
よくあるNG例|「具体的に見えない表現」
採用サイトで業務内容や仕事の流れを伝えようとするとき、抽象的すぎる表現や、業界用語に偏った説明は避けたいポイントです。ここでは、学生の理解を妨げてしまう「見えない表現」の代表例と、その改善案を紹介します。
NG例1:「モノづくりを支えるやりがいある仕事」
一見ポジティブに聞こえる表現ですが、実際にどんな製品を、どのように支えているのかが見えてこないため、印象に残りません。改善するなら「自動車部品の製造に必要な金型を設計・加工する仕事」のように、具体的に記述しましょう。
NG例2:「お客様のニーズに応える提案型営業」
「提案型営業」という表現は便利な反面、実際に何をどう提案しているのかが曖昧になりがちです。学生にとっては「飛び込み営業なのか?既存取引なのか?」といった疑問が残ります。製品数や提案の流れ、社内との連携など、リアルな情報を加えましょう。
NG例3:「地域社会に貢献できる仕事」
社会貢献をアピールすること自体は悪くありませんが、「何を通じて、どう貢献しているのか」が伝わらなければありきたりなコピーで終わってしまいます。たとえば「学校や病院に電気設備を提供し、災害時にも機能する安全な環境を支える仕事」など、具体化がカギです。
どれも「伝えたつもり」になりがちな表現ですが、相手の知識レベルに合わせて、背景や役割、成果まで落とし込んだ表現が大切です。
アトラボでは、図解・フロー・インタビューなど多角的に「仕組みの見える化」を設計します
仕事の仕組みが複雑な企業にこそ必要なのが、「視覚的・言語的にわかりやすく伝える」工夫です。アトラボでは、新卒求職者の視点に立って、複雑な構造や業務内容を多角的に整理・見える化し、採用サイトや採用情報ページに落とし込むお手伝いをしています。
図解・フローチャートで「全体像と自分の位置」を伝える
たとえば建設業の元請け・下請けの関係や、製造業の開発から量産までの流れなど、業界構造と自社のポジションを視覚的に示すことで、求職者が自分の仕事の「意味」や「価値」を理解しやすくなります。
インタビュー・ストーリーで「具体的な働き方」を伝える
実際に働いている社員の声を交えることで、「どんな工程に関わっているのか」「チームでどう連携しているのか」など、テキストでは伝えきれない“肌感”を伝えることができます。インタビューはもちろん、1日の流れやプロジェクト単位でのストーリー形式も有効です。
仕組みを伝える「構成設計」から一緒に考えます
単に原稿を書くのではなく、どのページで、どの段階で、どのように仕組みを伝えるかといった設計からご提案します。採用ページ全体の情報設計と連動させながら、御社の魅力がよりわかりやすく伝わるよう支援いたします。
「業界が複雑だから伝えづらい…」と諦める前に、図やストーリーを活用した“伝わる見せ方”を一緒に考えてみませんか?
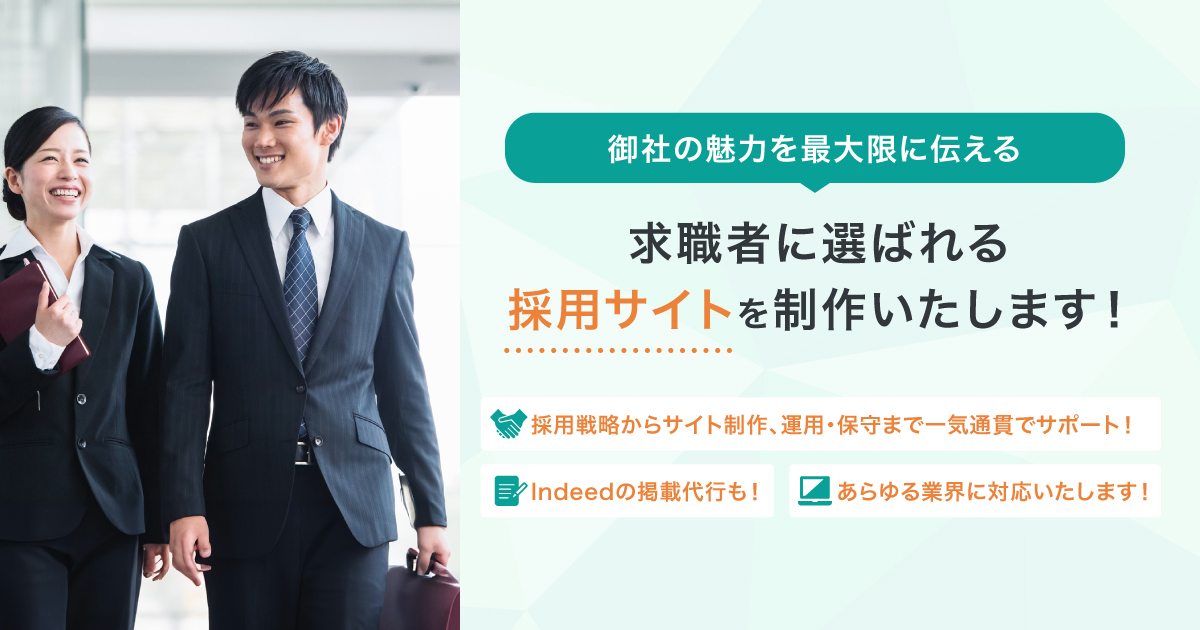
まとめ|“業界構造”を理解してもらうことが、志望の第一歩につながる
建設業、製造業、卸売業などに共通するのは、「仕事の仕組み」が複雑であるがゆえに、求職者からはその実態が見えづらいという点です。特に新卒採用においては、業界に対するイメージ不足が志望度の低下につながってしまうことも少なくありません。
だからこそ、採用ページでは自社がどんな立ち位置にあり、どんな役割を担っているのかを明確に伝える必要があります。図解やフロー、実際の社員の声などを活用することで、「自分にもできそう」「面白そう」という興味を引き出し、応募の背中を押すことができます。
複雑なことを、わかりやすく伝える。それが、“志望される企業”になるための第一歩です。
「どう見せたらいいかわからない」「素材が足りない」という場合でも、構成設計からアトラボがサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
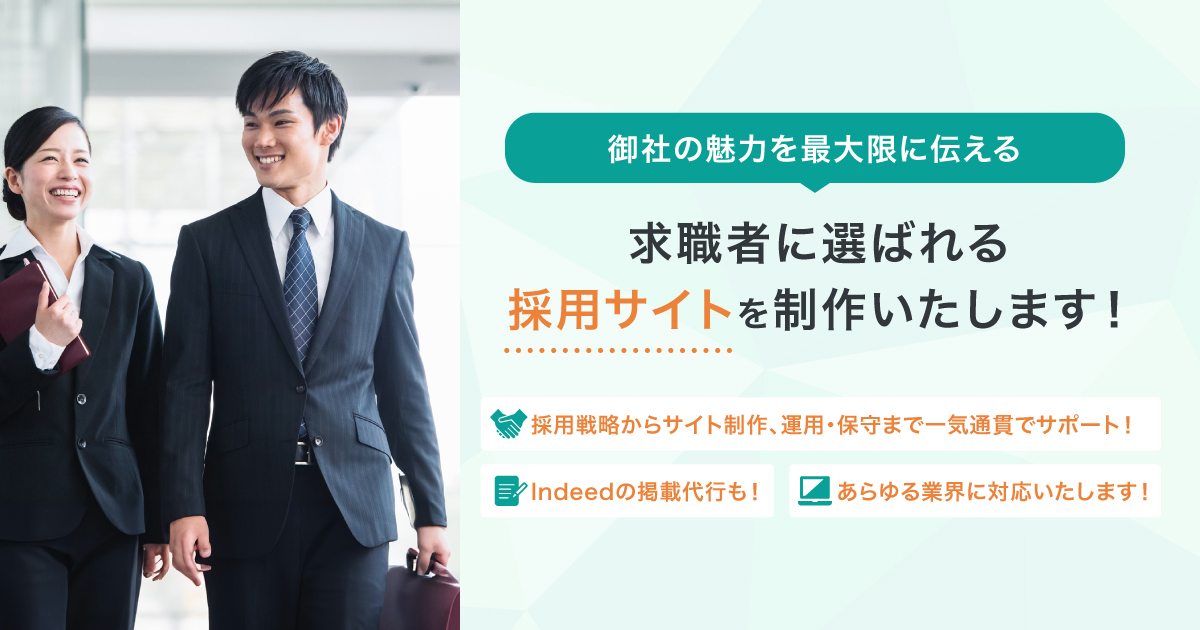




コメント