
コーポレートサイトを構成するページの中でも、「事業案内ページ」はほぼすべての企業サイトに存在すると言っても過言ではありません。企業のサービスや製品を紹介するこのページは、会社の「顔」となる重要なパート。しかし、見込み客や求職者の立場からすると、「ただ事業内容を羅列しただけのページ」では、必要な情報にたどり着けず、離脱されてしまうことも少なくありません。
特に最近では、Webを活用した営業活動や採用活動が当たり前になり、「事業案内ページ=読んでもらうため」ではなく、「行動してもらうため」のページとしての役割が強まっています。
本記事では、見込み客や求職者が知りたいことを的確に伝え、問い合わせや応募といった次のアクションへと導くために、どのように事業案内ページを設計すれば良いか、具体的なポイントを解説します。
「事業案内ページ」は“読んでもらう”より“動いてもらう”ページ
多くの企業が「事業案内ページ=会社の説明を丁寧に伝える場所」と捉えていますが、Webサイト上のこのページは、単なる読み物ではありません。最終的にユーザーに“行動”してもらうための導線設計が求められるのです。
例えば、製造業であれば「技術的な強み」や「対応エリア」などが明確であることで、問い合わせや見積依頼へのハードルが下がります。人材サービス業であれば、「どのような業種・職種に強いのか」「紹介実績や対応スピード」などが記載されていれば、資料請求や相談依頼につながりやすくなります。
ページの最終目的が「問い合わせ」なのか「採用応募」なのかによって、見せる内容や配置すべき要素は変わってきます。事業案内ページを設計する際は、単に情報を詰め込むのではなく、ターゲットの行動心理をふまえて、次のステップへ自然に進めるような構成にすることが重要です。
目的に合わせて分ける、3つのターゲット別設計パターン
事業案内ページは、訪問者すべてに同じ情報を届ける必要はありません。むしろ、どのターゲットに対して、どんなアクションを期待するのかを明確にし、情報を分けて設計することで、成果につながりやすくなります。以下に、よくある3つのターゲット別パターンをご紹介します。
1. 見込み顧客向け(BtoBの発注担当者・個人のお客様)
この層に向けたページでは、製品・サービスの内容が明確で、料金や納期の目安が把握しやすいことが重要です。導入事例や実績、お客様の声を紹介することで、信頼感を高めましょう。CTA(お問い合わせフォームや資料請求)も目立つ位置に配置し、行動を促す構成が効果的です。
2. 採用希望者向け(中途・新卒)
求職者は、単に「何をしている会社か」ではなく、「どんな環境で、どんな人が働いているのか」を知りたがっています。業務内容に加えて、働き方・キャリアモデル・社内の雰囲気などを紹介することで、応募への不安を軽減できます。採用情報ページとリンクさせる構成もおすすめです。
3. 取引先・パートナー企業向け
協力会社や仕入先など、パートナー候補となる企業が見る場合には、事業規模・対応エリア・設備体制などの信頼性を伝えることが重要です。「一緒に事業を進めていける相手か」を判断してもらえるように、事業ビジョンや安全管理への取り組み、外部認証などの情報も掲載しましょう。
このように、ターゲットと目的に応じた設計を行うことで、事業案内ページは単なる紹介ページから、成果につながるコンテンツへと進化します。
よくあるNG例:「紙のパンフレットの丸写し」では伝わらない
事業案内ページの制作でよくあるNGパターンが、紙の会社案内パンフレットのレイアウトや構成をそのままWebに流用してしまうことです。
紙のパンフレットは、展示会や対面営業の補助資料として使われることが多いため、一覧性を重視してサービスや事業の内容を“羅列”する形式になりがちです。しかし、Webサイトでは検索から訪れた見込み客が「自分に関係のあるサービスかどうか」を瞬時に判断したいと考えています。
たとえば、以下のような構成では成果につながりにくい傾向があります。
- 「サービスA」「サービスB」「サービスC」といった項目を並べるだけ
- それぞれのサービスの特徴や対象エリア、実績が書かれていない
- 導入事例や活用イメージがなく、イメージが湧かない
- 「詳しくはこちら」といったリンクや問い合わせへの導線がない
このような構成は、「何をやっているかはわかるが、自分に合うかどうかわからない」という印象を与えてしまい、結果として問い合わせを逃す要因になります。
Webの事業案内ページでは、サービスごとに「誰に向けたサービスか」「どのような課題を解決できるか」を明確に伝えることが重要です。また、具体的な事例や対象地域、導入までの流れなどもあわせて紹介することで、見込み客が安心してアクションを起こしやすくなります。
コンテンツ設計のコツ:誘導導線から逆算する
事業案内ページを作る際、最も重要なのは「最終的に何をしてほしいのか」を明確にすることです。「問い合わせ」「資料請求」「来店予約」などの導線を最初に決めておくことで、コンテンツ全体の設計方針がぶれなくなります。
たとえば「法人向けサービスへの問い合わせを増やしたい」のであれば、そのサービスを利用することで得られるメリットや他社との違い、導入までの流れを詳しく掲載し、最下部には「まずは資料請求から」や「導入事例集はこちら」など、行動につながるリンクを設置します。
逆に、誘導導線を決めずにコンテンツを積み重ねていくと、「説明は多いが何をしてほしいのかわからない」ページになってしまいがちです。これは非常にもったいないパターンです。
また、それぞれのセクションに目的を持たせることもポイントです。たとえば…
- 冒頭:訪問者に共感されるような課題提起とサービスの概要
- 中盤:サービスの強み・他社との違い・導入事例
- 後半:よくある質問や導入の流れ、問い合わせへの誘導
このように、訪問者の行動を促す「流れ」を意識して構成することで、事業案内ページは“読ませるページ”から“動いてもらうページ”へと進化します。
アトラボの視点:ターゲットごとに情報設計を変えています
株式会社アトラボでは、「誰に、どのような行動をしてもらいたいのか」を起点に、事業案内ページの情報設計を行っています。取引先の決裁権を持つ経営層に向けた構成と、現場担当者に伝えるべき技術的な内容では、同じサービスでも見せ方は大きく異なります。
また、採用を強化したい企業においては、求職者の目線から見た「仕事の魅力」や「現場の雰囲気」が伝わる構成にしなければ、事業案内ページもただの説明文で終わってしまいます。
アトラボでは、ヒアリング段階から「ページの目的」と「ユーザー像」を共有しながら、戦略的にページ設計を行うことで、企業の価値や強みが正しく伝わり、問い合わせや応募につながるサイトづくりをサポートしています。
今ある「事業案内ページ」を見直すだけでも、大きな改善のチャンスが眠っているかもしれません。ターゲットに響く情報設計を、ぜひご一緒に考えてみませんか?
まとめ
「事業案内ページ」は、単なる説明の場ではなく、見込み客や求職者の“行動”につなげるための重要なコンテンツです。誰に、どのような情報を伝えたいのか、そしてその結果どんなアクションを起こしてほしいのかを明確にすることで、ページの構成や文言も大きく変わります。
紙のパンフレットをそのままWebに転用するだけでは、検索流入やコンバージョンは見込めません。むしろWebだからこそ可能な、誘導設計やターゲット別の情報発信を活かすことが求められます。
アトラボでは、そうした「意図をもったページづくり」を重視し、クライアントの強みや目的に合わせたWeb戦略を一緒に考え、ご提案しています。事業案内ページを見直したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
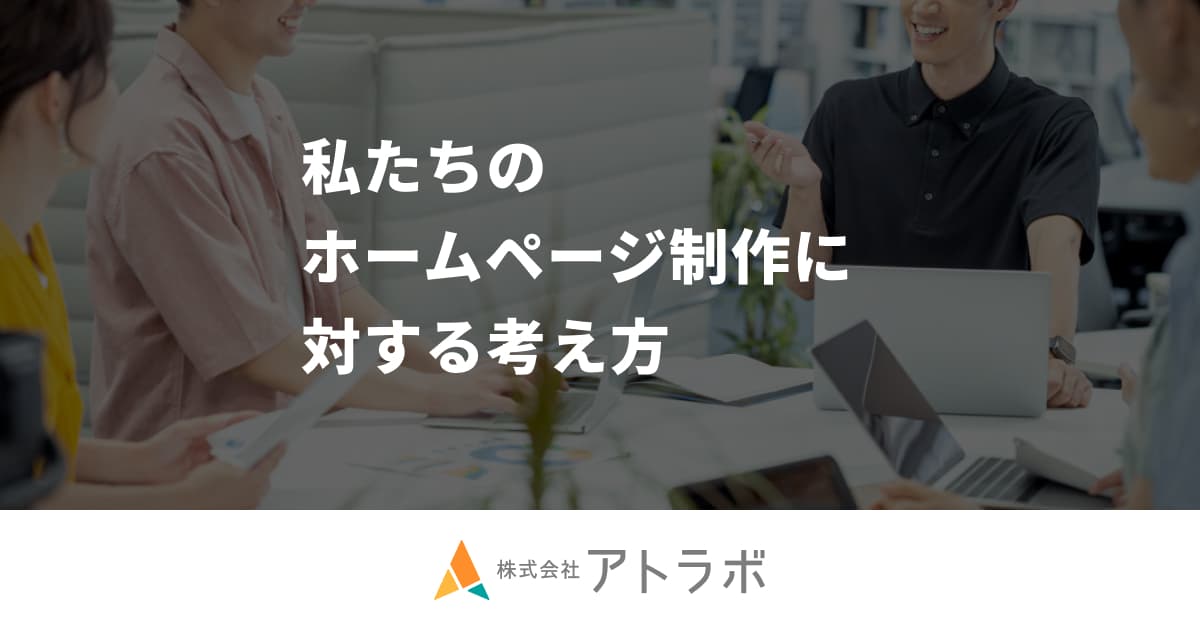




コメント