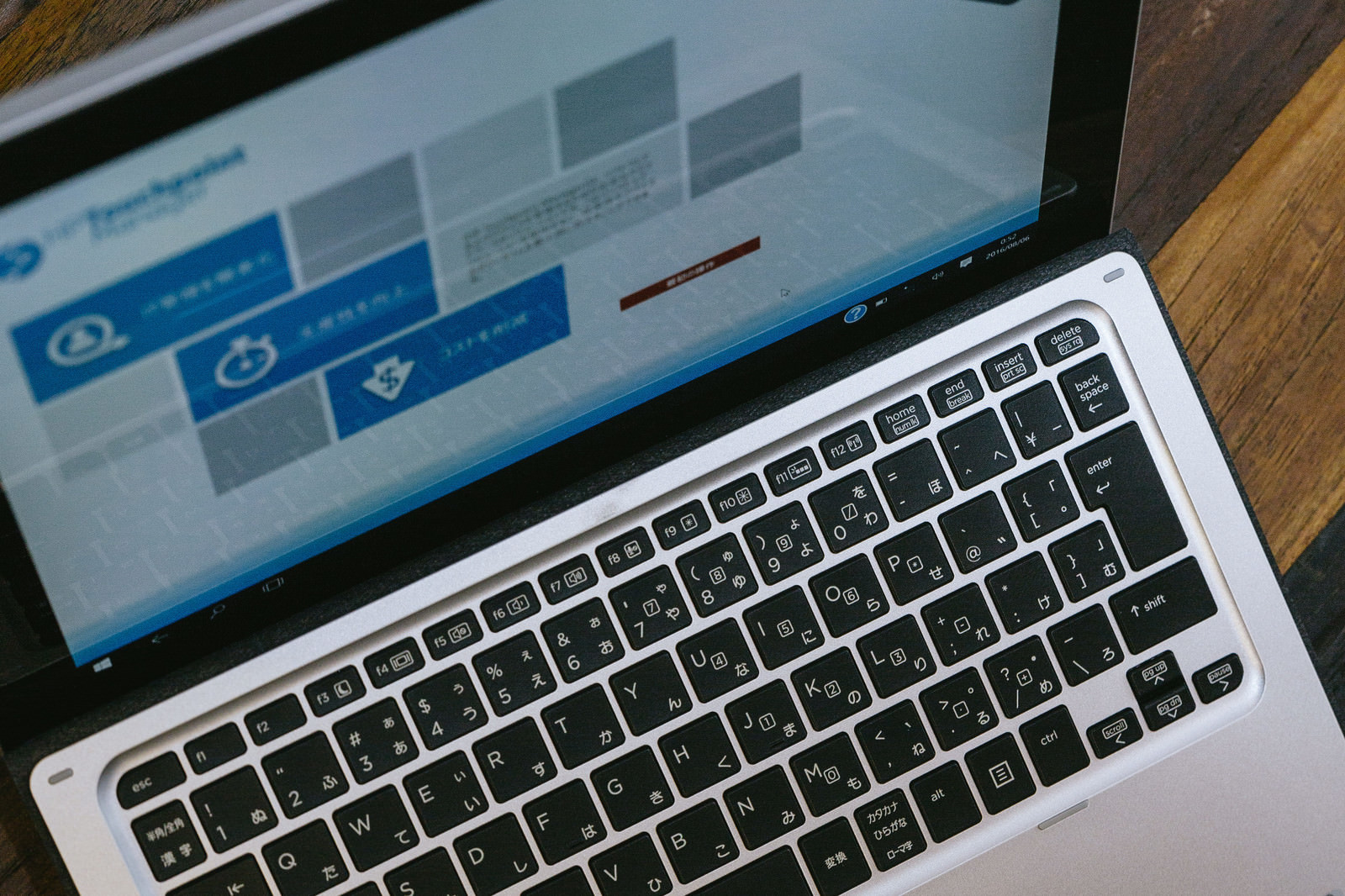
最近、企業のWeb戦略として「採用サイト」や「ECサイト」をコーポレートサイトとは別に立ち上げるケースが増えています。どちらも目的がはっきりしているだけに、「新しくドメインを取って別サイトにしよう」と判断しやすいからです。
ところが、いざ複数のサイトを持ってみると——
- メールアドレスとURLが合っていない
- 名刺やパンフレットの掲載情報がバラバラ
- デザインやブランドイメージに統一感がない
など、「同じ会社のホームページなのに、統一感がない」という“チグハグさ”が気になってくることも。
実はこれ、最初のドメイン設計で「ちょっと工夫」するだけで避けられたことかもしれません。
本記事では、企業が複数のWebサイトを運営する際に知っておきたい「拡張に強いドメイン戦略」を解説します。特に「サブドメインを活用する」ことが、今後のWeb展開にどれだけ大きな意味を持つかを、実例を交えながらご紹介していきます。
「Webサイトが増えてきた」中小企業のよくあるパターン
中小企業におけるWebサイトの増加は、事業の成長やターゲット層の拡大に伴って自然と起きるものです。特にBtoC向けの商品展開や採用強化が始まると、こうした動きが顕著になります。
【例1】コーポレートサイト+採用特設サイト
新卒・中途の採用活動を強化したいときに、「採用に特化した専用サイトを立ち上げたい」という相談は非常に多くあります。デザインや雰囲気もガラッと変えて、会社全体のブランディングとは少し違うトーンにしたいという要望も出てきます。
その結果、「recruit-◯◯◯.com」「◯◯◯-saiyo.jp」など、別ドメインでの採用サイトが誕生することも少なくありません。
【例2】BtoB企業がECサイトを新設
もともと法人向けに製品・サービスを提供していた企業が、新たにBtoC市場に進出し、自社製品をECで販売したいと考えるケースもよくあります。Shopifyなどの外部サービスを使って構築しやすいため、別ドメインをそのまま取得してECサイトを開設する流れになることが多いです。
例えば、「shop-◯◯◯.com」「brandname.shop」など、ブランドや商品に合わせた短いドメインが人気です。
【例3】プロジェクト単位でLP(ランディングページ)を次々立ち上げ
補助金・キャンペーン・新サービスなど、短期間のプロモーションを目的とした「単発型LP」を、都度新しいドメインやサブディレクトリで立ち上げていくパターンです。最初は軽い気持ちで「このプロジェクト用に1つ取っておくか」と始めても、2つ、3つと増えるごとに管理の手間が倍増します。
このように、目的に応じて複数のWebサイトを運営するのは自然な流れです。ただし、場当たり的にドメインを取得し続けていくと、「ブランドの統一感がなくなる」「SEOや運用が非効率になる」といった課題にも直面しやすくなります。
サブドメイン?サブディレクトリ?まずは基本の違いを知ろう
複数のWebサイトを運営する際に悩むのが、「別ドメイン」「サブドメイン」「サブディレクトリ」のどれを使うかという問題です。まずは、それぞれの違いをざっくり整理しておきましょう。
サブドメイン
たとえば、recruit.example.com や shop.example.com のように、メインドメインの前に別名をつけて管理する方法です。Googleも「別サイト」として扱いますが、メインドメインとの関連性は強く保たれます。
- メリット:運用上の自由度が高く、CMSの分離やデザインの切り分けがしやすい
- デメリット:SEO的には本体サイトとの評価が分かれる傾向にある(ただし近年は統合的に評価されるケースも)
サブディレクトリ
たとえば、example.com/recruit/ や example.com/shop/ のように、メインドメインの中に「階層構造」でページを追加していく方法です。Googleは「同じドメイン内のコンテンツ」として強く評価します。
- メリット:SEOの効果が本体サイトに集まりやすい。評価の一元化がしやすい
- デメリット:CMSの制限が多く、複数担当者での運用や大規模なデザイン変更には不向きな場合も
どちらを選ぶべき?
短期的なSEO効果を重視するならサブディレクトリ、
将来的な拡張性や運用分担を重視するならサブドメインがおすすめです。
たとえば「採用サイト」「ECサイト」のように役割が明確に異なる場合は、独立性の高いサブドメインが好まれる傾向にあります。CMSやセキュリティの構成も別にしやすいため、社内でも運用しやすくなります。
SEO的には?知っておきたい評価の考え方
Webサイトを分けたとき、「SEOの効果が分散しないか?」と心配になる方も多いでしょう。たしかに昔は、「1つのドメインにコンテンツを集約する方が有利」と言われることが多くありました。
Googleは「サブドメイン=別サイト」と見なす傾向
Googleの公式見解としては、サブドメインは基本的に「別のWebサイト」として扱われるというのが前提です。つまり、メインサイトのドメイン評価(ドメインパワー)を、そのままサブドメインが引き継ぐわけではないということです。
ただし、最近ではコンテンツの質やサイト間の関連性によっては、一定の評価が連動するケースも多くなってきており、昔ほど「分けたら損」という単純な話ではなくなってきました。
検索順位は「ユーザー視点」が重視される
近年のSEOでは、「このキーワードで検索するユーザーが、どんな情報を求めているか?」という文脈が非常に重視されます。そのため、
- 事業内容やターゲットが大きく異なる場合(例:法人向け建設と個人向けリフォーム)
- 集客の導線や問い合わせ窓口が異なる場合(例:採用と顧客)
などは、むしろ分けた方がSEO的にも理にかなっているケースが増えています。
評価が分かれるデメリットは「設計」でカバーできる
サブドメインを使う場合でも、適切に内部リンクを貼ったり、ナビゲーションやフッターで親サイトとのつながりを見せたりすることで、「企業としての一体感」を保ちつつSEOの弱点を補うことが可能です。
つまり、「分けるか、まとめるか」だけでなく、「どう設計するか」もSEOにとっては重要な視点なのです。
ネットショップや採用サイトで、サブドメインを選ぶことのメリット
ネット販売や採用活動に力を入れたいとき、「特設サイトを新たに立ち上げよう」と考える中小企業は少なくありません。その際、本体サイトとは別に作る特設サイトを、サブドメインで運用するという選択肢がとても効果的です。
ツールごとのドメイン事情と運用上の注意
たとえば、Shopify・カラーミーショップ・STORESといったネットショップ構築ツールでは、初期設定のままだと「◯◯.stores.jp」などのサブドメインが割り当てられます。これを自社ドメインに変えたい場合、
- 新たに別ドメインを取得して設定する
- 自社の既存ドメインのサブドメインを割り当てる
という2つの選択肢がありますが、後者の「サブドメイン」方式の方が、管理コスト・ブランド統一・SEOの観点でおすすめです。
サブドメインなら、ブランドの“ひとつなぎ感”が出せる
たとえば、以下のような使い分けができます:
- コーポレートサイト:
https://example.co.jp - ネットショップ:
https://shop.example.co.jp - 採用特設サイト:
https://recruit.example.co.jp
このように運用すれば、複数サイトであっても「同じ企業の一部」であることが明確に伝わりやすくなります。社名やサービス名での検索結果にも統一感が出るので、ユーザーの混乱も避けられます。
あとから整理するのは大変。最初に考えておくと楽
事業拡大とともに「あれも別ドメイン、これも別ドメイン」と作ってしまうと、ブランディングの一貫性が崩れたり、社内でのURL管理が煩雑になったりすることも。はじめから「サブドメインで増やしていける設計」にしておくことで、将来的にもスムーズなサイト運用が可能になります。
サブドメイン運用は、ブランディングにも有効
サブドメインの活用は、単なるコスト削減や管理の効率化だけでなく、企業のブランディング強化にも大きく寄与します。
“ひとつの世界観”で展開できる
たとえば、「https://shop.example.co.jp」「https://recruit.example.co.jp」といったように、すべてのWebサイトを一貫したドメイン配下で展開することで、「この会社のブランドだ」とひと目で分かるようになります。
特に最近では、ネットショップや採用ページ単体でSNS広告や検索広告を出すケースも増えており、リンクを踏んだ先が見慣れたドメインであれば、それだけでユーザーは安心感を覚えやすくなります。
別ドメインでは「関連性」が伝わりにくい
逆に、別ドメインで作った場合には、
- 「これは本当に公式サイト?」と不安になる
- 企業名で検索しても出てこない
- 他社と誤認されてしまう
といったリスクも。特にBtoCビジネスにおいては、第一印象が購入や応募の意思決定に大きく影響するため、ブランド名を含んだサブドメインで統一感を持たせておくことは非常に重要です。
“ドメイン設計”は、信頼と成果につながる
サブドメインは、ユーザーにとってもGoogleにとっても、「同じ企業の傘下にあるサイト」であることを明示できる強力なツールです。ブランドとしての認識や評価が積み重なりやすくなるため、長期的に見て、信頼性の蓄積にもつながります。
結論:初期設計の段階で「将来のマルチサイト化」を見据えよう
採用強化やEC進出など、企業活動が広がる中で「Webサイトが増えていく」ことは、ごく自然な流れです。だからこそ、初期段階で“ドメインの使い方”を設計しておくことが、後の運用負担やブランドの一貫性に大きく影響します。
「とりあえず別ドメインで作ったら、管理が煩雑に」「企業名がバラバラで、どれが本物かわからない」「メールの送信元やリンク先で不信感を持たれた」…こうした事例は決して珍しくありません。
Webサイトを複数持つ可能性が少しでもあるなら、将来のマルチサイト展開を前提とした“ドメイン戦略”を、最初から視野に入れるべきです。
そのための有効な選択肢のひとつが、今回紹介してきたサブドメインの活用。同じドメイン配下に複数サイトを展開することで、コストや手間を抑えつつ、ユーザーにも一貫した安心感を提供できます。
アトラボでは、事業展開を見据えたWeb設計もサポートしています
私たちアトラボでは、ホームページの制作だけでなく、企業の将来的な事業展開やマルチサイト化も見据えた設計をご提案しています。
「今は1サイトだけど、将来的にECサイトや採用サイトを追加するかもしれない」
「社内で複数の部署がそれぞれ情報発信したい」
そんな段階からご相談いただければ、サブドメインやサブディレクトリの活用、管理のしやすさ、ブランドの統一感、SEO面の影響などを総合的に考慮したドメイン設計をご提案することが可能です。
また、メールアドレスの一元管理やセキュリティ面の整備、将来を見据えたCMS(管理システム)の選定など、ただのホームページ制作にとどまらない「Web基盤整備」もお手伝いしています。
Webサイトを“資産”として育てていくために、ドメイン戦略は重要なスタート地点。
気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ|ドメイン戦略は“増える前”に考えておこう
事業が成長するにつれて、Webサイトが1つだけでは足りなくなる場面はよくあります。採用特設サイト、ECサイト、サービスごとの専用ページなど、サイトが“増える”こと自体は、むしろ企業としての前向きな展開です。
しかし、そのたびにバラバラのドメインで立ち上げてしまうと、管理が煩雑になったり、ユーザーにとって分かりにくい印象を与えてしまったりすることも。また、SEOやブランド統一という面でも不利になる可能性があります。
そうならないために、最初の段階で「サブドメイン」という選択肢を知り、将来を見据えたドメイン戦略を立てることが重要です。ドメインは一度取得すれば、長く使い続けるもの。だからこそ、初期設計の段階でしっかりと計画しておくことが、後々のWeb運用のスムーズさと成果に直結します。
アトラボでは、中小企業のフェーズに合わせた柔軟なドメイン設計や、複数サイトを前提としたWeb戦略のご相談も承っています。Webまわりの将来設計で不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。


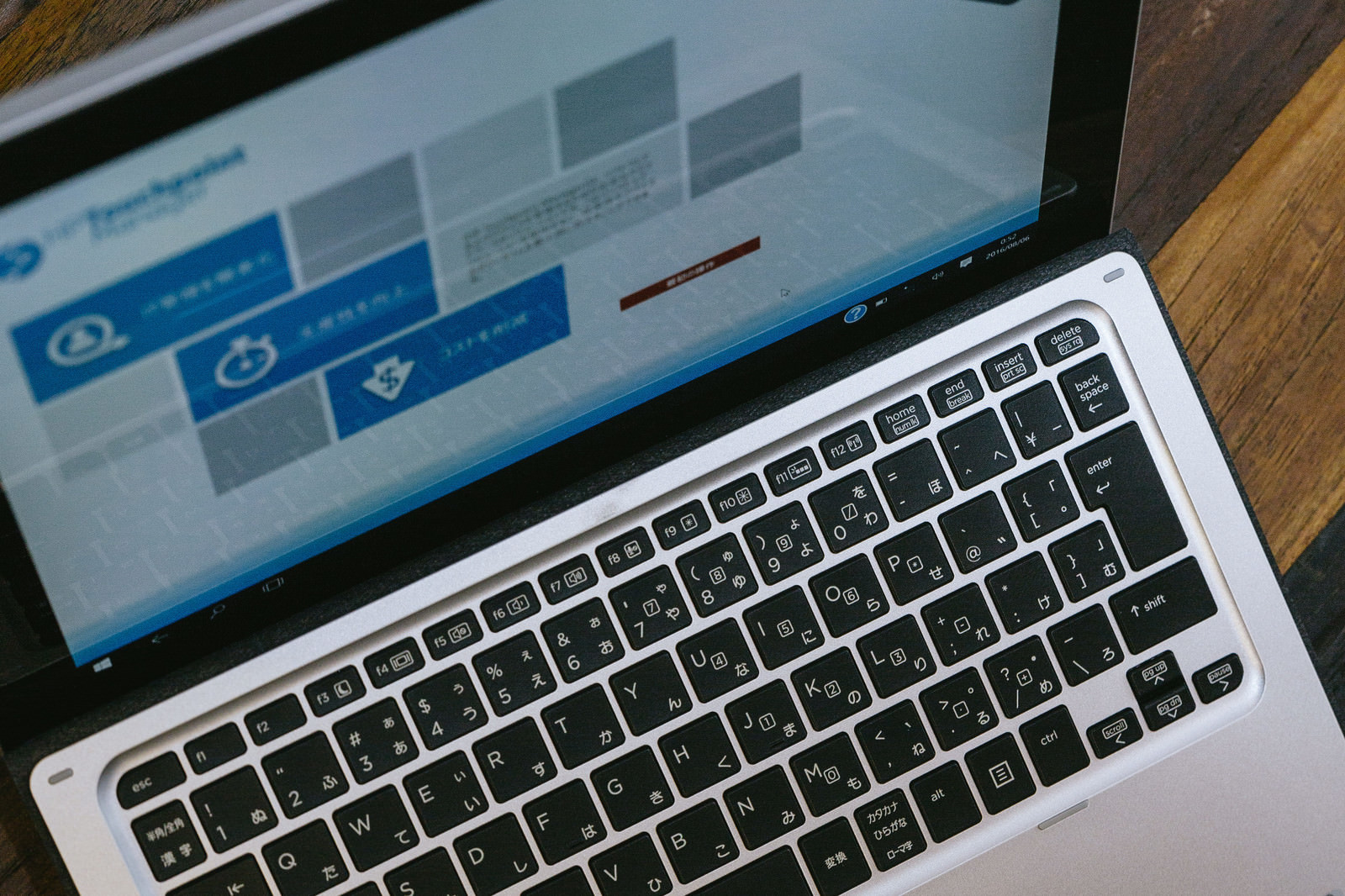


コメント