
「求人を出しても若い人が来ない」「応募があってもすぐ辞退される」——そんな悩みを抱える企業は少なくありません。特に中小企業や地域密着型の企業にとっては、若手人材の確保は年々ハードルが高くなっているのが現実です。
そこでつい、採用活動の見直しに走ってしまいがちですが、本当に変えるべきはそこでしょうか?SNSでの広報や求人票の表現を工夫しても、会社自体の雰囲気や将来性が伝わらなければ、若手の心には響きません。
むしろ問題は、職場環境や組織そのものにあるのかもしれません。「若手が活躍できそうにない」雰囲気が漂っているなら、いくら求人票を磨いても意味がないのです。
本記事では、“採用活動”の前に見直すべき企業の姿勢、組織文化、そして経営の視点について掘り下げていきます。若手に選ばれる企業とはどんな企業なのか?その本質に迫ります。
採用だけが頑張っても、組織全体が古ければ意味がない
「SNSで発信してます」「採用ページもリニューアルしました」——こうした採用部門の努力が水の泡になるケースは少なくありません。その原因は、組織全体の“空気”が変わっていないからです。
例えば、面接時の対応が年功序列的で、「まずは下積みから覚えようか」といった言葉が飛び交う、あるいは配属される部署が数十歳上の社員ばかりで、会話のテンポすら合わない…そんな職場環境では、どれだけ採用担当ががんばっても若手の共感は得られません。
若手にとっての「働きやすさ」は、制度以上に“空気感”です。意見が言いやすいか、相談できる先輩がいるか、自分の意見が何かしら形になる可能性があるか。これらが感じられない職場では、「ここで働いても自分は成長できない」と判断されてしまうのです。
本気で若手を採用したいのであれば、採用部門だけでなく、組織全体のマインドセットを変える必要があります。「若手を迎える準備ができているか?」それが今、企業に問われているのです。
若手が避ける「老朽化した組織」の5つの共通点
企業の成長を止めるのは、外的環境だけではありません。内側から徐々に時代遅れになってしまった組織には、いくつか共通する特徴があります。若手が「入りたくない」「定着したくない」と感じる要因は、以下のような点に集約されます。
1. 情報共有が紙ベース、または口頭
業務連絡がホワイトボードや紙のメモ、電話や口頭に頼っていませんか?若手世代はリアルタイムで記録が残るチャットツールやクラウド管理に慣れています。アナログな情報伝達は「効率が悪い会社」と捉えられてしまいます。
2. 上司=絶対、という力関係
若手が意見を言いづらい上下関係、場の空気を読むことが重視される社風は、現代の価値観から大きくズレています。「自分の存在が消される感覚」は、離職の大きな原因になります。
3. 評価制度が不透明、年功序列
「頑張っても報われない」職場に、成長意欲の高い若手が魅力を感じるはずがありません。評価制度が年齢や勤続年数に依存している場合、将来への展望が持てず、モチベーションが低下します。
4. 新しい技術やツールの導入に消極的
ITツールや業務改善の提案がスルーされる、または導入しても使われない。そんな企業は「変化できない組織」と見なされ、若手から敬遠されがちです。彼らは効率化を前提に働き方を選んでいます。
5. “やりがい搾取”に近い社風
「昔はもっと大変だった」「気合で乗り越えろ」など、精神論がベースのマネジメントは通用しません。きちんと報酬や待遇に見合う期待をすることが、フェアな関係構築に不可欠です。
これらの特徴は、単なる「古さ」ではなく、若手から見て「自分たちとは合わない」と判断される根拠になっています。組織の“老朽化”に気づき、見直すことが最初の一歩です。
“採用”よりも“事業”をアップデートせよ
「若手が来ない」と嘆く企業の中には、そもそも今の若手が魅力を感じるような“事業内容そのもの”に課題があるケースが少なくありません。どれだけ採用広報を工夫しても、「今の仕事に未来があるのか?」「この会社で成長できるのか?」という視点で見たとき、若手が魅力を感じられない事業は選ばれないのです。
特に、業界自体が斜陽化している、事業の柱がひとつしかない、付加価値をつけず価格競争に巻き込まれている…そんな構造的な弱さがある場合、採用活動より先に、事業戦略そのものの見直しが求められます。
新規事業や業務改善が採用戦略になる
たとえば、製造業でも「DX支援の一環で自社のIoT化を進めている」「海外取引を開拓している」といった事業変革の動きがあれば、それだけで若手の興味関心を引く材料になります。「変わろうとしている会社」「未来に目を向けている会社」という印象が、採用における最大のブランディングになります。
つまり、人を採るために事業を変えるのではなく、「人が来るような事業」に進化させることが、本質的な採用改善です。採用を単独の取り組みとせず、事業や経営の方向性とセットで考えることが必要不可欠です。
「人が来ない」と悩む前に、「来たくなるような事業になっているか?」を問い直すことが、今の時代に求められているアプローチではないでしょうか。
変革の鍵は「未来志向の社長」の覚悟と行動
組織を変えるには、社員全体の意識改革も必要ですが、何より重要なのは経営トップの意思と覚悟です。若手の採用に成功している中小企業の多くは、社長自身が「このままでは会社の未来はない」と本気で危機感を持ち、自ら学び、外部の知見を取り入れ、行動しています。
「ウチには若手が来ない」ではなく、「来たくなるような会社に変わるには、何をすべきか?」という問いに向き合い、採用だけでなく事業、制度、組織文化まで見直す
これまでのやり方に誇りを持つのは大切なことですが、それを若手に強要するのではなく、「これからの時代に合うやり方」にアップデートしていく柔軟さが必要です。「教える側も一緒に学び直す」姿勢が、若手にとっては安心できるポイントでもあります。
いきなりすべてを変える必要はありません。まずは社内のルールを1つ変えてみる、若手向けの企画を始めてみる、オフィス環境を見直してみる…。「変えようとしている姿勢」そのものが、求人情報よりも強力なメッセージになります。
そしてその姿勢を、採用サイトやSNSなど、社外にもきちんと発信していくことが、共感を生み、応募へとつながるのです。
組織を変えるには、社員全体の意識改革も必要ですが、何より重要なのは経営トップの意思と覚悟です。若手の採用に成功している中小企業の多くは、社長自身が「このままでは会社の未来はない」と本気で危機感を持ち、自ら学び、外部の知見を取り入れ、行動しています。
「ウチには若手が来ない」ではなく、「来たくなるような会社に変わるには、何をすべきか?」という問いに向き合い、採用だけでなく事業、制度、組織文化まで見直す
これまでのやり方に誇りを持つのは大切なことですが、それを若手に強要するのではなく、「これからの時代に合うやり方」にアップデートしていく柔軟さが必要です。「教える側も一緒に学び直す」姿勢が、若手にとっては安心できるポイントでもあります。
いきなりすべてを変える必要はありません。まずは社内のルールを1つ変えてみる、若手向けの企画を始めてみる、オフィス環境を見直してみる…。「変えようとしている姿勢」そのものが、求人情報よりも強力なメッセージになります。
そしてその姿勢を、採用サイトやSNSなど、社外にもきちんと発信していくことが、共感を生み、応募へとつながるのです。
若手が定着しない、そもそも応募が来ない──。それは“魅力がない”のではなく、「若手が活きる場所」が見えていないことが原因かもしれません。何も、会社の全体像を根本から変えなくても、ちょっとした工夫で「ここなら自分も活躍できそう」と思わせる場は作れます。
たとえば既存の業務の一部や、新しい商品アイデア、SNSアカウント運用など、社内のサブプロジェクトを若手主体で動かせる仕組みをつくるだけで、「意見が言える」「裁量がある」職場として魅力が増します。はじめから責任を重くしすぎず、小さく成功体験を積ませるのがポイントです。
上司世代が「自分たちのやり方こそ正しい」と固執していては、若手の挑戦意欲はしぼんでしまいます。むしろ、上の世代も新しい技術や働き方を学び直す姿勢を見せることで、若手にとっても安心して質問・相談しやすい環境になります。
「若手とベテランの価値観のズレ」はどの職場にもあります。そこで有効なのが、“世代間の通訳”になれるミドル層の育成です。間に立って双方の意図を汲み取って翻訳できる存在がいれば、対立は減り、若手も居場所を感じやすくなります。
つまり大切なのは、「若手向けの環境はつくれない」と諦めないこと。今あるリソースを見直すだけで、十分に変化のきっかけをつかむことができます。
若手が応募してこない。入ってもすぐに辞めてしまう。
求人票の書き方を工夫する前に、まずは職場の環境づくり。「ここで働いたら、こう成長できそう」と感じてもらえるビジョンや、変化を恐れない経営姿勢こそが、次世代の人材を惹きつける本質的な要素です。
アトラボでは、単なる採用サイト制作にとどまらず、企業の採用戦略そのものをデザインする視点で、中小企業の皆さまをご支援しています。「若手が活躍できる職場をつくりたい」という想いがあるなら、まずはお気軽にご相談ください。変化を拒むのではなく、受け入れる
小さなチャレンジからでも変革は始まる
変革の鍵は「未来志向の社長」の覚悟と行動
変化を拒むのではなく、受け入れる
小さなチャレンジからでも変革は始まる
今あるリソースで「若手が活きる場」を作る工夫
小規模プロジェクトを任せる仕組み
「学び直し」を社内に根づかせる
世代間コミュニケーションの橋渡し
まとめ:変えるべきは“求人票”ではなく“企業の未来像”
その原因を「求職者側のミスマッチ」や「最近の若者は…」と捉えていては、問題はいつまでも解決しません。必要なのは、自社が「未来に挑戦しようとしている組織」かどうかを、冷静に見つめ直すことです。
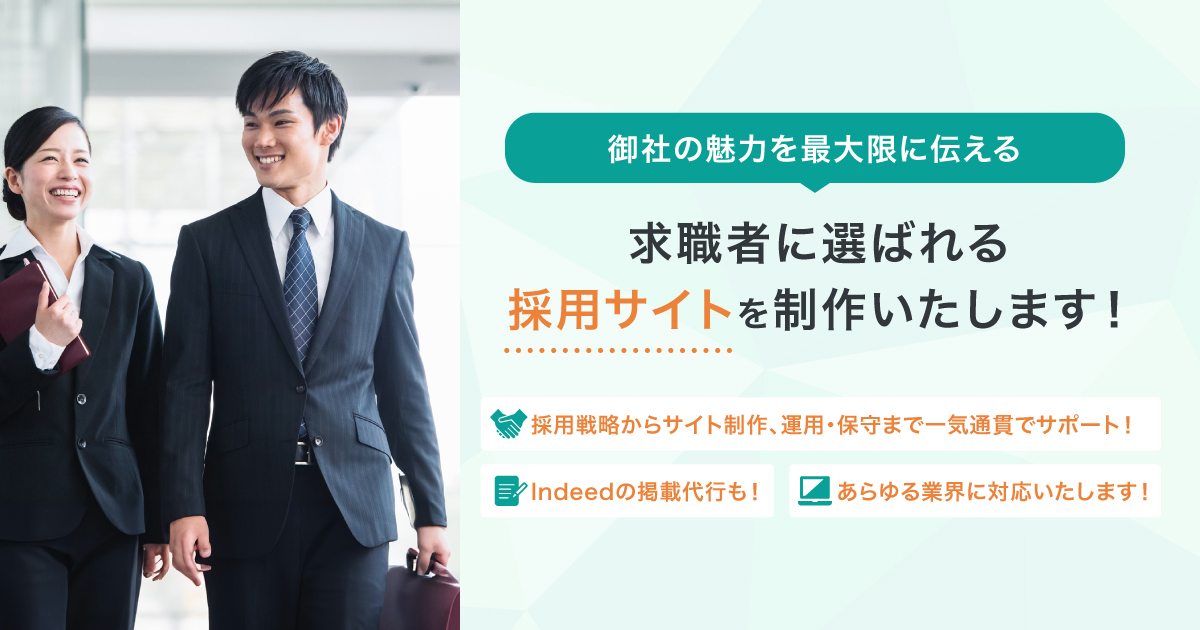




コメント