
「求人サイトに掲載しても応募が来ない」「せっかく採用サイトをつくったのに、見てもらえていない気がする」——そう感じたことはありませんか?
近年の採用市場では、従来の求人ポータルサイトや合同説明会だけで人材を集めるのが難しくなっています。特に若手求職者は、自分で企業を調べ、口コミやSNSの発信を見てから「応募するかどうか」を決めるケースが増えています。
そんな中で注目されているのが、X(旧Twitter)を活用した採用広報です。
Xは、日々のちょっとした出来事や社員の素顔を“つぶやく”ことで、企業の雰囲気や人柄を自然に伝えることができます。文章が短くても拡散力が高く、フォロワーが少なくても多くの人に届くチャンスがあるため、中小企業でも無理なくスタートできるSNS戦略として注目されています。
特に最近は、BtoBの製造業や建設業などでも、若手向けの採用ブランディングにXをうまく取り入れて成果を出している例が増えてきました。
本記事では、「採用目的でXをどう活用するべきか?」という視点から、中小企業が今すぐ取り組める発信方法や運用のコツをご紹介します。採用につながる“つぶやき力”を育てたい方は、ぜひ最後までお読みください。
X(旧Twitter)だからこそ「気軽な距離感」が作れる理由
採用活動において、求職者が企業に対して感じる心理的ハードルは意外と高いものです。特に中小企業の場合、「どんな会社かよくわからない」「話しかけづらい」と思われてしまうと、せっかく良い企業でも候補にすら上がりません。
X(旧Twitter)には、そんな“壁”を壊す力があります。
■ 「ゆるい接点」を作れるSNS
Xは、Instagramのようにビジュアル重視でもなく、Facebookのようにかしこまる必要もありません。「今日の現場は暑かった!」「新入社員が一人立ちできました」など、日常の出来事をカジュアルに共有できるSNSだからこそ、求職者との“ゆるい接点”を自然に生み出すことができます。
特に若年層は、企業に対して「情報の量」よりも「人の雰囲気」や「空気感」で親近感を持つ傾向が強いため、Xのような“つぶやき”スタイルが有効です。
■ DM機能で気軽な質問・相談の入り口に
Xのもう一つの利点は「DM(ダイレクトメッセージ)」の存在。アカウント側がDMを開放しておけば、求職者からの質問や相談が気軽に届くようになります。
実際に、採用広報でXを活用している企業では、「応募する前に質問したい」「会社の雰囲気を知りたい」というDMが増えており、応募者との初期接点として活用されています。
■ 「会社の中の人」の発信が効く
Xは、企業アカウントとしてではなく、「中の人」(広報や現場社員)の個人アカウントから発信するスタイルも有効です。
「〇〇工業 広報アカウント(中の人)」のような表記であれば、堅苦しさを避けつつ、企業との距離感を縮めることができます。
企業公式アカウントであっても、発信内容に「社内の人間らしさ」がにじむと、リプライや引用RTなどの反応も得やすくなり、コミュニケーションが活発になります。
■ 拡散されやすく、広がる可能性がある
Xは「リポスト(旧リツイート)」文化が根付いているため、たとえフォロワーが少なくても、発信が“誰かの目に留まれば”一気に広がる可能性があります。
求人情報やイベント告知を投稿するだけでなく、日常のエピソードを織り交ぜて発信することで、偶然見た人が「面白い会社だな」「雰囲気が良さそう」と感じてくれることも。
このように、Xは“求職者との距離”を自然に縮めるのに最適なメディアであり、採用サイトや求人広告では届かない層にも企業の魅力を届けることができるのです。
採用広報として「発信すべきネタ」とは?
Xを活用する上でよくある悩みが「何を投稿したらいいのかわからない」というものです。しかし採用広報の視点で見れば、“ネタ”は社内に無数にあります。
重要なのは、求職者にとって“働くイメージが湧く”情報であること。以下に、実際に効果のあった発信内容を分類してご紹介します。
■ 社内の日常風景やエピソード
- 「今日は事務所の模様替え!みんなでワイワイやってます」
- 「現場終わりにラーメン会🍜 こういう時間も大事にしてます」
- 「入社1年目の〇〇くんが初めてプレゼンに挑戦!」
社員の自然な表情や、職場の雰囲気が伝わる発信は、求職者にとって非常に魅力的です。華やかでなくても、等身大の空気感が刺さります。
■ 若手社員の声や働き方に関する情報
- 「若手社員にインタビュー!『うちの会社、意外と○○なんです』」
- 「研修終わりました!来週から現場デビューです💪」
- 「20代中心でやっている現場の様子、今日はこんな感じ」
若年層の求職者が共感しやすい“近い先輩”の姿は、特に新卒や第二新卒層に響きます。
■ 社外イベントや地域との関わり
- 「地元の清掃ボランティアに参加してきました🧹」
- 「高校生向けインターン説明会に登壇しました!」
- 「地域のものづくりイベントに出展中です!」
中小企業ならではの地域とのつながりや、社会貢献の姿勢も好感を持たれやすいポイントです。
■ 求人情報や採用イベントの案内
- 「2026年度新卒採用スタートしました!エントリーはこちら▶︎」
- 「今週末、会社説明会を開催します!まだ枠あります!」
- 「DMでの質問もOKです。お気軽にどうぞ!」
“告知だけ”の投稿に偏らず、上記のような発信と組み合わせることで、自然に流入が増える構成を意識しましょう。
■ 経営者やリーダーの“考え方”や“人柄”が見える言葉
- 「うちの会社は“人を育てる”ことを本気でやっています」
- 「社長として大切にしていること。それは〇〇です」
- 「採用は未来への投資。だからこそ本気です」
求職者にとって、社長の考え方や会社の価値観が垣間見える投稿は、安心感や共感につながります。
■ 「誰が投稿するか」もポイント
公式アカウントであっても、“誰が投稿しているか”が見えると反応率が上がります。
「〇〇(総務部)がつぶやいてます!」や「中の人=広報の山田です」など、親しみやすさを演出することで、DMなどのアクションにもつながりやすくなります。
発信内容に「正解」はありませんが、大切なのは“求職者目線”で何を伝えるべきかを常に意識することです。
Xで求職者と“つながる”ためのポイント
拡散力や気軽さが魅力のXですが、ただ投稿しているだけでは「求職者とつながる」ことはできません。フォローされ、読まれ、反応されるためには、いくつかの工夫が必要です。ここでは、求職者との接点を作るためのポイントを整理してご紹介します。
■ プロフィールと固定投稿を“入口”にする
プロフィール欄には、会社の業種や特徴、採用活動をしていること、DM相談歓迎である旨などを簡潔に書いておきましょう。
また、固定ツイート(ピン留め)には「募集職種」や「会社説明ページ」のURLを載せることで、アカウントに訪れた人がすぐに情報へアクセスできます。
■ DM(ダイレクトメッセージ)は開放しておく
最近では、学生や若手求職者が「気になる企業にDMで質問する」という流れも増えています。
フォロー外からのDMも受け付ける設定にしておくことで、「ちょっと聞いてみたい」という声を拾うきっかけになります。
■ 返信・引用RT・いいねで“会話”をつくる
一方的な発信だけでなく、他の企業や就活生アカウントへのリアクションも大切です。
例えば、採用イベントに関する投稿を見つけたら「うちも参加します!」と引用RTしたり、インターンに関する投稿に「がんばってください!」と返信することで、アカウントに“人”を感じてもらえるようになります。
■ 「中の人」が見えるようにする
「〇〇部の●●が投稿してます」など、アカウントの“中の人”が誰かを示すことで、親しみやすさと信頼感が生まれます。
ときどき「今日はこんな業務をしていました」など、担当者自身の声も交えると、アカウントに“温度感”が出てきます。
■ フォロワーを「数」ではなく「質」で見る
大企業のように数万フォロワーを目指す必要はありません。
大切なのは、地元志向の学生や業界に関心のある若手など、将来応募につながる層と“濃いつながり”を築くことです。
たとえ数百フォロワーでも、定期的に反応してくれるファンができれば、それは立派な採用資産になります。
■ ハッシュタグや就活ワードを戦略的に使う
「#24卒」「#就活垢さんと繋がりたい」「#地元就活」などのハッシュタグは、検索からの流入を促すための強力なツールです。
企業側から使うのに少し勇気がいるかもしれませんが、見てもらえる機会を広げる意味では非常に効果的です。
Xは“情報発信ツール”であると同時に、“コミュニケーションツール”です。
つながりをつくるには、求職者の目線に立った丁寧な運用が求められます。
無理なく続けるための社内体制づくり
X(旧Twitter)を採用広報に活用しようとすると、「誰が更新するのか」「どれくらいの頻度で投稿するのか」「ネタはどうするのか」など、運用面での不安が出てきます。実際に活用できている企業は、どこも“無理のない体制”を社内で工夫しています。ここでは、そのための考え方と仕組みづくりのポイントを紹介します。
■ 担当者を決めるより、“チーム”で運用する
「SNS担当者を一人に任せきり」にすると、プレッシャーや属人化で止まりやすくなるのが現実です。
そこでおすすめなのが、広報チームや人事メンバー、若手社員を巻き込んだ“小さなチーム運用”。
「投稿内容は月1回ミーティングで決める」「素材は現場スタッフにLINEで送ってもらう」など、分担しながら運用の負荷を分散すると、継続しやすくなります。
■ 投稿ネタを“ストック型”で管理する
その場の思いつきで投稿しようとすると、どうしてもネタ切れになります。
社内の出来事や行事、現場風景、求人の告知など、あらかじめ「ネタのタネ」を一覧化しておくと、必要なときにすぐ発信できます。
GoogleスプレッドシートやNotionなどを活用して、投稿案や下書きをストックしておくと便利です。
■ 投稿テンプレートを決めておく
「この曜日は“社員のひとこと”」「このタグは会社紹介」など、投稿の型を作っておくことで、考える負担を減らし、運用のハードルを下げることができます。
あらかじめテンプレート化しておけば、複数人で投稿を担当してもトーンや方向性をそろえやすくなります。
■「社内で見てもらう」意識を持つ
SNSは外部向けの発信ツールではありますが、社内のモチベーションアップや空気づくりにも効果があります。
「今日の投稿、○○さんが映ってましたね!」「あのツイート面白かったです」など、社内でも投稿を共有・反応するような文化が生まれると、自然と継続しやすくなります。
■ 「最初の数か月はトライ&エラー」と割り切る
最初から成果やバズを狙うのではなく、まずは運用に慣れることが大切です。
フォロワー数やエンゲージメントにとらわれすぎず、「毎週1回は更新する」「写真1枚+ひとこと」など、自分たちのペースを作ることを意識しましょう。
SNSの運用は、スポットでなく“マラソン”のような継続型の取り組みです。
無理なく続けられる体制をつくることが、結果的に求職者との信頼関係を築く一番の近道になります。
「炎上」「誤投稿」などのリスク対策
SNS、とくにX(旧Twitter)を企業アカウントとして活用する場合、どうしても気になるのが「炎上」や「誤投稿」などのリスクです。
実際に、多くの中小企業では「もし問題が起きたらどうしよう」「社内の誰が責任を取るのか分からない」といった懸念から、せっかくの広報チャンスを活かせていないケースもあります。
ここでは、必要以上に怖がらず、実行可能な範囲で備えておくべきリスク対策を紹介します。
■ 投稿前の「ダブルチェック」を習慣化する
もっとも基本的な対策は、投稿前に必ず別のメンバーが内容を確認するルールを作ることです。
誤字脱字はもちろん、表現に問題がないか、公開タイミングに誤りがないかなど、Wチェック体制を取るだけでも、トラブルの多くは未然に防げます。
■ 社内向けの「投稿ガイドライン」を作成しておく
炎上の多くは、悪意よりも“無自覚な投稿”が原因となるケースが目立ちます。
「この話題は避ける」「撮影前に本人の了承を取る」「DM対応は人事担当者のみ」など、社内ルールを明文化しておくと安心です。
難しいマニュアルである必要はなく、簡単なA4一枚程度のチェックリストでも効果があります。
■ 炎上・クレーム時の「対応フロー」も決めておく
万が一、投稿内容に対して否定的な反応やクレームが入った場合は、誰が、どう対応するのかを明確にしておくことが重要です。
広報、総務、経営層が連携できるように、連絡系統や削除判断の基準など、あらかじめ合意を取っておくと冷静に対応できます。
■ 社員個人アカウントとの“切り分け”を徹底する
採用広報において「社員が個人アカウントで企業のPRをしてくれる」のはとてもありがたいことですが、その発言が“公式の見解”と誤解されないように注意が必要です。
「公式アカウントとの明確な違い」「発言内容の制限」「リプライ・引用RTの制限」など、線引きを共有しておくことが、不要な混乱を防ぐポイントです。
■ それでも「ゼロリスク」にはならないことを前提に
SNS運用におけるリスクをゼロにすることはできません。
しかし、“リスクより、得られるメリットの方が圧倒的に大きい”のがSNS、特にXの特徴です。
だからこそ、大きな事故を防ぐ最低限の対策をとった上で、前向きにチャレンジしていく姿勢が求められます。
リスクを理由に何もしないのではなく、「備えて、使いこなす」ことが、今後の採用活動の差につながっていくのです。
SNSが苦手でもOK!まずは「Xで採用広報」から始めてみよう
「SNS運用はなんとなく苦手…」「人手も時間も足りないし、毎日投稿なんて無理…」
そんな中小企業の採用担当者こそ、まずはX(旧Twitter)での発信から始めてみるのがおすすめです。
Xの魅力は、「完璧じゃなくても伝えられる」気軽さにあります。
インスタグラムのようにビジュアルに凝る必要もなく、TikTokのような動画編集スキルも不要。スマホひとつで、日常の中にある“採用につながるエピソード”を、そのままの言葉で届けられるのが、Xの強みです。
例えば、こんなつぶやきでも十分価値があります。
- 「今朝の現場は快晴!新卒くんが今日はじめてひとりで担当。がんばれ!」
- 「工場でのお昼ごはん。今日は〇〇さんの差し入れのスイカが登場」
- 「来週は見学会です。興味ある方、DMでどうぞ!」
何百人に見てもらわなくてもいいのです。「ちょっと気になるな」「感じがよさそうな会社だな」と思ってくれる“未来の仲間”が1人でも増えることが、採用広報の第一歩です。
最初は週1投稿でも、DM対応だけでも構いません。
自社の「空気感」や「働いている人のリアル」が伝わる発信を、少しずつでいいので継続していくことが、求人票では伝えきれない「人となり」や「信頼感」を育てる最短ルートなのです。
SNSが苦手でも大丈夫。まずは、ひとつ「会社の日常を届ける場所」として、Xを開設してみませんか?
アトラボでは、SNSと連動した採用ブランディングも支援しています
アトラボでは、ただの「投稿代行」ではなく、採用サイトや会社パンフレット、エントリーフォームなどと連携した、一貫性のある採用ブランディングをご提案しています。
特にX(旧Twitter)のようなSNSは、採用活動の“顔”にもなりうるツールです。
だからこそ、投稿内容・トーン・デザイン・ハッシュタグの選び方まで、ターゲットに合わせた細やかな設計が欠かせません。
弊社では、以下のようなサポートを行っています。
- 採用ペルソナに基づいたSNS運用設計(投稿テーマ・頻度・運用フロー)
- 社員インタビューや撮影との連動による投稿素材の提供
- 採用サイト・募集要項・エントリーフォームとの統一感ある導線設計
- ハッシュタグや投稿文面の最適化(X初心者でも安心)
採用活動の効果を高めるには、「点」ではなく「線」での設計が重要です。
SNSを単独で運用するのではなく、採用広報全体の戦略と連動させていくことで、より多くの“共感”と“信頼”を獲得することができます。
「SNSを始めたいけど、何から始めればよいかわからない」
「採用サイトやパンフレットと連動させたい」
そんな企業様は、ぜひアトラボにご相談ください。

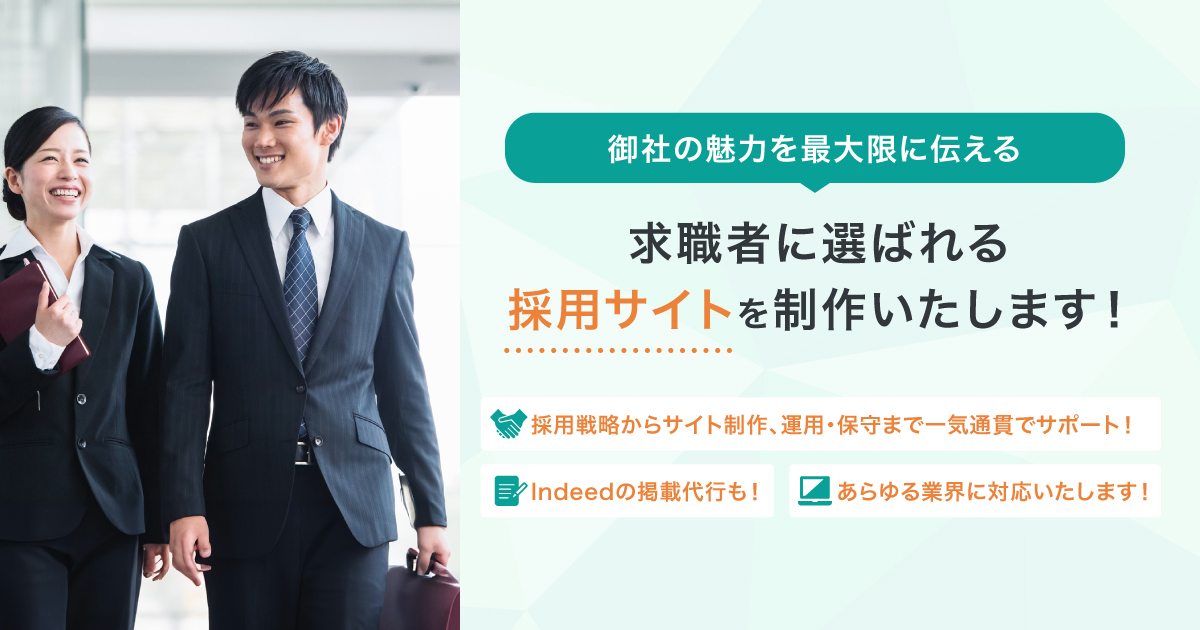
まとめ:Xは“採用に効く”コミュニケーションツール
X(旧Twitter)は、今や単なるSNSではなく、企業と求職者がリアルな距離感でつながる「採用広報の実践ツール」です。
とくに知名度や予算に限りのある中小企業にとっては、ブランディングや共感づくりの大きな武器となり得ます。
ただし、単にアカウントを作って投稿すれば良い、というものではありません。
誰に向けて、何をどう伝えるか、そしてそれをどう継続し、どのように採用導線と連携させていくか。
この設計があってこそ、Xは「つながり」を生み、「応募」へと導く力を発揮します。
アトラボでは、SNS運用単体ではなく、採用ブランディング全体を視野に入れたサポートをご提供しています。
「まずはXから始めてみたい」「採用サイトとSNSをうまく連携させたい」——そんなご相談も、お気軽にどうぞ。
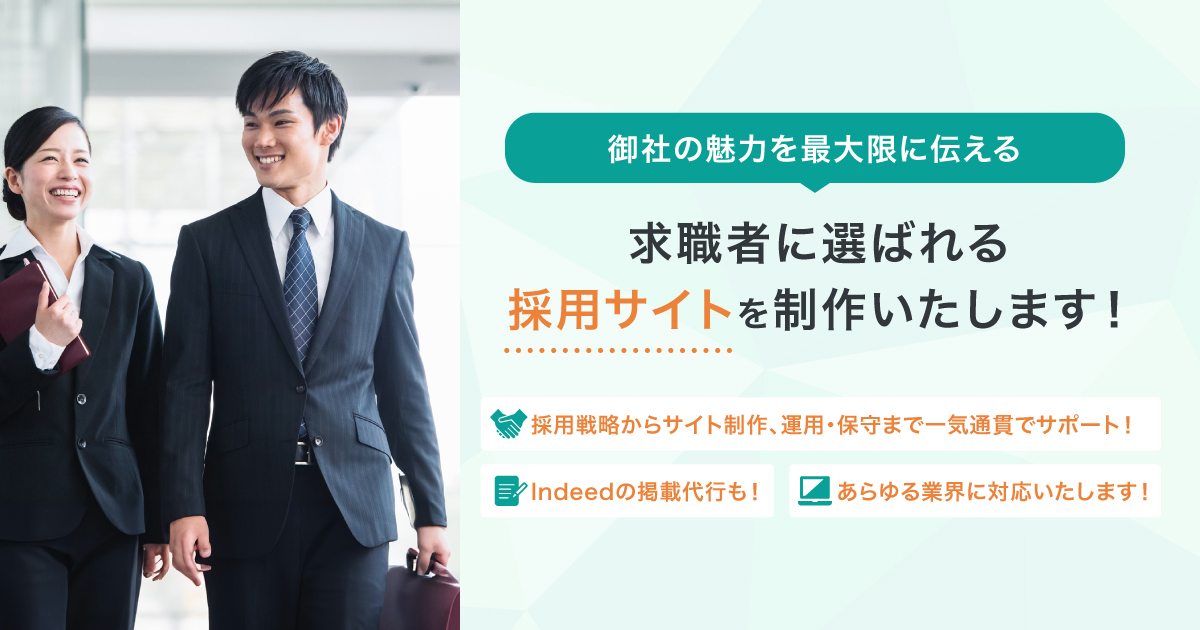





コメント